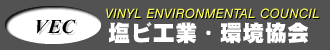 |
NEW VEC MAGAZINE Vol.13
発行年月日:2004/01/29
|
|
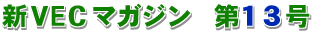
|
| 今月のメニュー |
| 塩ビ産業、半世紀(50年)を越えて その2 |
|
|
−協会に35年間在籍して− |
|
|
|
太田泰正 |
|
| ■コラム |
| 塩ビ産業、半世紀(50年)を越えて その2 |
|
|
−協会に35年間在籍して− |
|
|
|
太田泰正 |
3.塩ビ製造の技術革新
○塩ビ製造技術の革新
塩ビ製造技術での大きな革新は68〜70年にかけこれまでのカーバイド法による塩ビモノマー製造は電力料金の値上がりからコストが高く、アメリカのエチレンを原料にして二塩化エチレン(EDC)を合成して塩ビモノマーを製造するエチレン法を導入し、あるいは塩ビ製造各社が開発した自社技術を採用して、これまで電力の関係から北陸に集中していた塩ビ製造工場は、太平洋沿岸のコンビナートに拠点を移し運搬コストなどの合理化が図られると共に量産体制が整った。
そして、この頃、重合技術は生産性をあげるべく塊状重合や連続重合技術について盛んに研究がなされたが、結局は量産するには大型化しかなかったようである。
以後大型化へ急速に転換し、信越化学の130m3缶が74年に完成される。
最近は、100〜150m3缶が主流で、一部に200m3クラスもある。
また、80年ごろの生産性は進んでいた技術で1ヶ月に1m3あたり20〜25トン、これに比べ現在では同40〜50トンと見られる。
何と2倍の生産技術の革新がある。
○環境問題に対応
塩ビモノマーの原料は塩素である。この塩素を製造する苛性ソーダ工業から排出される水銀が、68年に環境問題としてクローズアップされた。ソーダ業界がただちに取った施策は水銀を系外に出さないクローズドシステム化であり、さらにその後水銀を使用しない隔膜法及びイオン交換膜法への製法転換が図られ水銀問題は解決した。これは世界でも我が国だけである。
次いで塩ビモノマーの発がん性問題がアメリカの塩ビ製造メーカーの従業員から80年に肝血管肉腫(アンジオサルコーマ)が発症した。
ここでお断りしておくが、このアンジオサルコーマは塩ビ製造従業者に発症する極めてまれなもので、塩ビモノマーに高濃度、かつ長期間(平均20年以上とのデータがある)暴露されてはじめて発症するもので、これまで一般住民が発症したとの事例は全世界で一件もない。
この対策としては、塩ビモノマーを系外に排出しないよう工程の密閉化、塩ビモノマーを含む排出ガス回収設備の設置また、レジン中の残留モノマー反応終了後スラリーの脱塩ビモノマー処理技術を確立し、業界全体で145億円の設備投資を行った。
さらに、現在、環境省及び経産省の指導のもと95年より塩ビモノマーはじめ有害12物質について第一期削減計画が終了して現在第二期(01〜03年)の削減計画にて基づき削減計画を実施している。
更に、環境ホルモンの疑いがもたれた可塑剤は03年6月に厚生・労働省より環境ホルモンでないことが発表されている。
4.将来の展望
先にも述べたように、塩ビは硬質から軟質製品に至るまで広範囲に利用され、特に塩ビ製品は建材のパイプを始め床材及び壁紙などの市場では独占状態であった。このため他のプラスチックが塩ビの同用途に入り込む余地が無く、後発のプラスチックメーカーの羨望の的ならよいのだが何かにつけ煙たがられることになる。
例をあげれば、麻雀はいつも一人勝ちでいると嫌われるの例えで、そういう意味では入り込める余地を残しておくことも必要である。
塩ビ以外のプラスチックもそれぞれすばらしい素地をもっているのでその性質を伸ばせるような用途に使うべきであり、塩ビとそれ以外のプラスチックとの利用に現在は棲み分けが出来ているとみられる。塩ビの用途と同じ用途でということであれば物性なり使い良さ、価格面など塩ビより優れた素材が登場すればそれにとって代替されるのは当然と考えられる。
○新用途開発の必要性(まとめに代えて)
これまで述べてきたように建材に利用される塩ビが市場を独占してきたと同時に、塩ビ樹脂以外のプラスチックがその役割を担うには無理であった。そのため建材分野は唯一塩ビ忌避の影響を蒙らなかった、さらに塩ビ樹脂の最大の特徴である長寿命、耐久性に優れた物性を生かしたパイプ、壁紙及び床材などの土木関係や住宅建設への利用が大きいが、さらなる難燃性や物性の向上を追及していくことが必要である。
幸いに塩ビ建材は塩ビ需要の約6割を占めておりこの分野を維持・拡大していくと共に現在、窓枠及びサイデング等新規用途も芽生えつつありこれらを育てていくと共に新規用途の開発が必要である。
また、これらに利用した素材が、将来解体され廃棄物として排出され一部はリサイクルされ、一部は処分(現在は埋立)されている。
速やかにリサイクル(MR,FR,TR)されるシステム(製造−使用(新規)−利用(張替え)−解体−回収−再利用)の循環体制を一刻も早く確立すべきである。
経済的な貢献とともに、国民と産業とともに環境面でも歩調を合わせ、次世代に受け継がれる素材産業であり続けることを願っている。 |
|
| ■生活バンク・FPの部屋 |
ファイナンシャルプランナ−(略FP)、長谷部和子
|
| 『金融商品・収益性』 |
| りスクと引換えに高利回りや売却益を期待する。 |
|
前回までは、安全・安定性を重視した金融商品を述べてきましたが、今回から収益性を重視した積極運用型商品を見ていきます。
このような商品は投資対象を分散させる事が重要です。また価格変動りスクを軽減させる有効な方法は、投資時期を分散させます。
|
| (1) 株式投資 |
|
最も代表的なリスク商品です。
日本企業株は配当金額が低いので長期保有の投資ではなく、一般的には売買差益を求める投機的な商品となっています。
株式投資は上記のように、銘柄を分散し購入時期を分散して好きな銘柄を見つけて買って見てください。
|
| (2)債券投資(此処で言う債券は事業会社の社債です) |
|
債券は、いつ、幾らで買ったとしても発行会社が倒産しなければ、満期償還時まで保有した場合は国債等と同様に、毎年一定の利息が支払われ満期時には償還されます。このように、その時々の金融情勢に応じた利回りが確実に得られるので、預貯金と同列で比較的安全性は高い商品と言いえます。しかし、債券投資は発行された後、原則として自由に時価で売買されるので、この時価が金融情勢に応じて大きく変動する事があるので安全商品とはいえません。言い換えれば、途中売却する場合の債券は株式等と同様に価格変動商品であり、リスク・リタ−ン共に大きな商品です。(特に満期時までの残期間が長い債券ほど金利変動が大きく動く商品なので注意が必要です)
|
| * |
転換社債・・普通社債と違い『株式に転換出来る権利』という面がある。つまり発行時に決められた、一定の条件でその発行会社の株式に転換することができる社債です。そこで、その発行会社の株式を潜在的に保有している事を意味します。しかし、転換社債は株式と違って社債の価値が下がってくると、その利回りが上昇してくるため債券として(利回り面)の魅力が高まるという二面性を持っています。 |
| * |
新聞の株式欄と転換社債欄の両方で、経済情勢によって各社の株価と共に社債がどう動くかを見てください。 |
|
| ■読者便り |
| Q: |
塩ビのリサイクルについて質問です。
パイプ、農ビ、電線のマテリアルリサイクルが昔から民間活力で進んでいるのはよく判りました。また塩ビ管・継手協会の全国的な取り組みによって、塩ビ管がグリーン調達法の特定調達品目(公共工事)に追加されましたね。また、壁紙・床材・窓枠・雨樋が再資源化指定表示製品に定められているようですので、今後に期待できますね。
ところで、その他の塩ビ製品のリサイクルをどう考えていますか? |
|
|
|
A:
|
塩ビ樹脂用途の60%はパイプなどを含む建材、つまり建築材料、建設資材です。これらの使用済み塩ビ製品は、その排出時には混合廃棄物として他の素材と分別されずでてきます。したがってリサイクルは難しく、これまでは埋立てや焼却炉で処理されてきました。現在ではダイオキシン法も整備され、安全な処理処分が行われています。
しかし、埋め立て処分場の延命が喫緊の国家的課題となっている今、混合廃棄物の埋め立てや焼却をできるだけ減らすため、リサイクルが重要です。
そのひとつとして、JFEによる塩ビの高炉原料化、住友金属によるガス化溶融など、次世代技術の開発をVECは推進してきました。いずれも廃塩ビをふくむ混合廃棄物を受け入れ、高温で部分酸化します。そして炭素、水素、一酸化炭素、塩素などの化学原料に戻す、という意味でケミカルリサイクルと言われています。
実用化されるまでには、回収、再生、販売の各分野で、様々の検討が必要です。VECはこのプロセスに協力していきます。
|
|
☆読者便りは、VECホームページのお問い合わせから構成されています。
ご意見・ご質問をお待ちしております。
|
|
| ■お知らせ |
| 塩化ビニル環境対策協議会 国連大学セミナー |
| 「環境問題 ─ 何が最も重要か!」 |
前号でもご案内致しましたが、まだ空きがございますのでお時間ございましたら、ご参加頂きますよう、ご案内致します。 |
| ○ |
開催期日 |
: |
平成16年2月2日(月)16時〜19時 |
| ○ |
会 場 |
: |
国際連合大学 国際会議場 |
|
|
〒150−8925
|
|
|
渋谷区神宮前 5−53−70
|
|
|
電話 03(3499)2811
|
|
|
(交通)
|
地下鉄銀座線、千代田線、半蔵門線
|
|
|
|
表参道駅下車 B2出口より徒歩約5分 |
|
1. |
講 師
|
国際連合大学副学長 工学博士 安井 至 先生
|
|
|
演 題
|
「環境問題、何がもっとも重要か」
|
|
|
時 間 |
16:00〜17:20
|
|
2. |
講 師 |
読売新聞 編集局科学部次長 小出 重幸 氏 |
|
|
演 題 |
「メディアから見た環境問題の扱い方」(仮題)
|
|
|
時 間 |
17:30〜18:10
|
|
3. |
立食パーティー 18:30〜 |
|
|
|
終了後、同大学2階「レセプションホール」にて、18:30より立食パーティーを開催致します。
|
| 申込方法 |
下記アドレスまで貴社名・所属・役職・氏名・ご住所・ご連絡先(電話番号・FAX)をご記載頂きお申込み下さい。 |
| 参加費 |
講演会、パーティー共無料 |
| 問合せ先 |
事務局 関
|
|
TEL
|
03(3297)5601 |
|
FAX
|
03(3297)5783 |
|
| ■VEC関連URL |
|
|
| ■VECマガジン登録解除 |
|
|
| VEC |
VYNYL ENVIRONMENTAL COUNCIL
|
| 塩ビ工業・環境協会 |
|