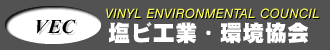 |
NEW VEC MAGAZINE Vol.16
発行年月日:2004/04/28
|
|
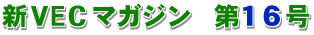
|
| 今月のメニュー |
| ■
|
コラム |
|
「かすかな変化、確かな変化」 |
|
−魚のメス化の本当の理由と化学物質の排出の減少− |
|
高橋裕明 |
|
「塩ビサッシと複層ガラスを家の標準仕様に」 |
|
−民生分野のCO2排出削減の切り札として中央環境審議会で合意− |
|
樹脂サッシ普及促進委員会 |
|
| ■コラム |
|
「かすかな変化、確かな変化」
|
| −魚のメス化の本当の理由と化学物質の排出の減少− |
|
東京では、桜のシーズンも終わったが、釣りはこれからがシーズンである。春告げ魚と呼ばれるメバルの夜釣りも楽しい。仕掛けを投入し、全神経を竿先に集中させると「ピクピクッ」「コツコツッ」と指先にかすかに伝わってくる。この感触がたまらない。一気に、「ガツーン!」とくる東京湾のシーバスとの格闘も熱くなる。
さて、最近の新聞(朝日新聞4月3日夕刊)に、東京湾の魚にみられる「メス化」現象の記事が載っていた。ここでいうメス化とは、オスの精巣内に卵細胞が形成される段階のことで、オスが完全にメスになったことではない。一般に、魚の性は遺伝子ではっきり決まっているものではなく、孵化するときの水温で決まったり、若いときはメス、年をとるとオスになるなど様々な要因が関与するという。(化学物質の影響を云々する前に)「野生生物の正常な現象を知るべきである」と昨年の環境省主催の「環境ホルモン国際シンポジウム」で話題になったほどである。ともかく、東京都環境科学研究所の調査結果によれば、魚メス化の主な原因は、下水処理水に含まれる天然女性ホルモン(エストロゲン)の可能性が高い。人工化学物質が環境ホルモンとして注目されがちだが、生態系保全のためには天然女性ホルモン対策が必要であるとの主張が紹介されていた。
事実、人工化学物質としてよく取上げられるノニルフェノール、ビスフェノールAはエストロゲンの一種であるエストラジオールと比べ作用強度は1万倍も小さいとも言われていることから、川に住む魚のメス化の原因はこのような人工化学物質ではなく天然女性ホルモンであるということは、多くの研究者の間では常識化していたことであるが、一般の人たちにはなかなか伝わってこないものである。そんな折、海に住む魚のメス化も、実は、天然女性ホルモンによる影響が大きいとのこの新聞記事は、環境ホルモン=人工化学物質となんとなく信じ込んでいた人たちにとっては、まさに「目からうろこ」ではなかったのではないだろうか。ダイオキシン問題ではないが、ようやく冷静な報道がなされるようになったと感心させられた。報道姿勢に確かな変化を感じている。
話はそれるが、化学物質というといつも化学業界だけが注目されがちだが、3月末、環境省と経済産業省から02年度の化学物質の排出量・移動量(いわゆるPRTRデータ)の集計結果が発表された。届出対象事業者(いわゆる工場)からの排出量は29万トンである(うち公共用水域への排出量は1.2万トン)が、届出対象外の事業者(規模の小さな工場)および自動車、一般家庭からの排出量はその倍の約59万トンと推定されている。これらの化学物質の大部分は大気への排出であり、前述の魚のメス化現象とは関係ないものの、人にとっても生態系の環境保全の立場からも、企業では化学物質の排出量削減に鋭意取組んでいる(01年度と比べ排出量が7%減)。もはや、造りっ放しの世の中ではなくなってきているのである。そんなことから、我々自身も日常生活の中で気付かないうちに化学物質の排出に関与していることを認識し、生活パターンを見直すなどそれなりの工夫が必要ではないかと考えてしまう。
|
|
「塩ビサッシと複層ガラスを家の標準仕様に」
|
| −民生分野のCO2排出削減の切り札として中央環境審議会で合意− |
|
皆さん、塩ビサッシという言葉を耳にしたことがありますか、複層ガラスは?
環境に興味をお持ちで、自ら進んで地球環境なかんずくCO2排出の抑制を、ご自身の日々の生活で実行しようと考えられておられる方々。
自信を持って、家の断熱に取り込んでください。
3月10日に開かれた中央環境審議会地球環境部会(部会長 浅野直人 福岡大法学部教授)で、家の断熱が民生分野のCO2排出削減の切り札と合意されました。
数字を見てみましょう。住宅・建築物の省エネ性能の向上で、年間3,560万トンのCO2を削減する目標を示しています。原油換算で860万klの削減。対策の例示として、樹脂(塩ビサッシ)と複層ガラスの普及を謳っています。
欧州では、この塩ビサッシと複層ガラスが家の標準仕様になっています。この窓の断熱はCO2排出抑制という“地球益”にとどまらず、家族の大事な健康を守ることにもなります。皆さん、ご自宅の窓をご覧になったことがありますか。朝、窓枠に結露していませんか。結露が、かび、ダニの原因にもなります。これが塩ビサッシ、複層ガラスにすることによって、大方防ぐことができます。
窓を断熱にした方の生の言葉もご紹介できます。
是非、樹脂サッシ普及促進委員会までご相談ください。
電話:3297-5781、FAX:3297-5783 ホームページ:http://www.jmado.jp
|
|
| ■環境バンク・セミナ−報告 |
FP&環境システムプロデュ−サ−・長谷部和子
|
FPの部屋を終了して16年度は環境セミナー報告を致します。
セミナ−の主題は、環境問題の根本は快適生活とエネルギ−消費のバランスをどう図るかです。どのような問題提起があり、その解決策が示されるか否か!
皆様ご期待ください。 |
|
| 16年度 前期6回・慶應義塾大学セミナ− |
|
主催: |
慶應義塾大学 開放環境科学専攻 環境・資源・エネルギー・科学専修 |
|
後援: |
横浜市環境保全局 |
|
企画: |
株式会社テムス(環境コミュネーケーションセンター) |
|
テ−マ:『地球環境保護とエネルギー多消費は両立するか』 |
|
|
|
−慶應義塾大学大学院・開放科学先行環境・資源・エネルギー専修とはー |
|
|
環境・資源・エネルギー に関わる、「分子レベル」から「地球規模」に至るまでの諸問題を研究・教育の対象としている。
理工学をベースとしながらその枠に留まらず、総合的な視点から問題解決に取り組んでいる。専任教員19名、大学院生約100名 |
|
今回のセミナ−の趣旨 |
|
|
生産活動・経済活動の急膨張の結果、「資源」と「環境」の両面で、いよいよ地球の許容限界が見えて来た。
資源・エネルギーの有効利用、地球環境保全のための戦略的取り組み、それを支える技術の根拠となる知識、およびその基盤となる研究・教育が緊急に求められている。
上記問題を大学及び企業など、様々な角度から今後考察する。
|
|
|
| ■読者便り |
| Q: |
現在塩ビ製品とおもちゃなどで使われている可塑剤であるクエン酸アセチルトリブチル(ATBC)とは何ですか?加工性や強度などについても教えてください。 |
|
A:
|
ATBC(クエン酸アセチルトリブチルAcetyl TriButyl Citrate、CAS.NO 77-90-7)は米国FDA(食料医薬品管理局)の認可を受けた、直接的および間接的に食品に接触して使用できる可塑剤です。
FDAの認可は、1種類以上の動物について、長期にわたる毒性試験により満足な結果が得られたものにのみ与えられます。従って、ATBCは食肉用包装材、おもちゃ、医療用用途、などに使用される塩ビ用可塑剤として有用です。
無毒、無臭、配合の容易さ、そして比較的安価という特徴を持っています。
お問い合せのATBC配合の軟質塩ビの加工性や機械的強度はフタル酸エステル系可塑剤(DEHP)を配合した物と比べて大差はありません。
一例として、ATBCおよびDEHP配合物の物性を比較しますと次のようです。
|
|
(Unitex データより) |
|
| |
ATBC50%配合物 |
DEHP50%配合物 |
Durometer A, 10sec
(硬度) |
78 |
79 |
Modulus at 100% elongation(psi)
(100%モジュラス) |
1348
(94kg/cm2) |
1368
(96kg/cm2) |
Tensile Strength (psi)
(引張り強度) |
2862
(200kg/cm2) |
2748
(192kg/cm2) |
Ultimate Elongation (%)
(伸び) |
400 |
395 |
Brittle Point (℃)
(揮発温度) |
−18.5 |
−24.5 |
|
|
なお、詳細はATBC取扱い企業にお問い合せ下さい。一例として下記2社をご参考下さい。
|
|
|
森村商事(株) http://www.morimura.co.jp |
|
|
Unitex Chemical Corporation http://www.unitexchemical.com |
|
☆読者便りは、VECホームページのお問い合わせから構成されています。
ご意見・ご質問をお待ちしております。
|
|
| ■お知らせ |
| ○ |
講演会 |
|
日 時 |
: |
平成16年6月14日(月) |
|
場 所 |
:
|
虎ノ門パストラル 新館5F「マグノリア」 |
|
講 演 |
:
|
慶應義塾大学 理工学部 機械工学科 教授
|
|
|
|
|
工学博士 川口 修 氏 |
|
|
|
「都市ごみの焼却処理について」
|
|
| ■VEC関連URL |
|
|
| ■VECマガジン登録解除 |
|
|
| VEC |
VYNYL ENVIRONMENTAL COUNCIL
|
| 塩ビ工業・環境協会 |
|